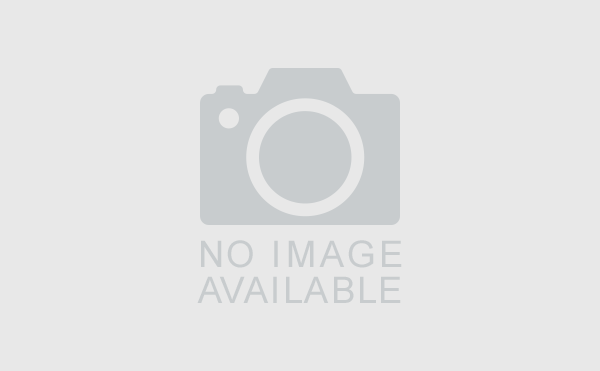第3回定例会一般質問 2025.9.11 そね文子
シスターフッド杉並の一員として、
- HPV(子宮頸がん)ワクチンの薬害から区民を守る取り組みについて
- 外国ルーツの子どもの学習支援について一般質問いたします。
まずはHPV(子宮頸がん)ワクチンの薬害から区民を守る取り組みについてうかがいます。
2010年から2013年にかけて多くの少女たちに子宮頸がんワクチンが打たれ、接種後に副反応被害が相次いだことを受け2013年6月、安全性に課題があることから子宮頸がんワクチンは積極的にお勧めしないという措置がとられました。しかし2022年4月からその同じワクチンの積極的勧奨が再開されました。また、積極的勧奨が中止されていた期間に接種を受けなかった年代の人たちにもキャッチアップとして接種が進められてきています。2023年4月からは新たに9価ワクチンのシルガード9が定期接種となり現在これらのワクチン接種がさかんに宣伝され、進められています。しかし2013年6月に重篤な被害が多数出たときとワクチンは同じものであり、新たに加わったシルガード9は旧来型のガーダシルの成分を約2倍に増量したもので安全性には懸念があります。実際、はしかや風疹など、ほかの定期接種12種類の平均に比べHPVワクチンの副反応疑い報告の頻度は、厚労省が発表している資料を元に計算すると88.3倍、そのうち入院治療以上を必要とする重篤なものの頻度は7.4倍という多さです。厚労省が作成したリーフレットにも、接種後に重い症状が起きることがあること、広い範囲の痛み、手足の動かしにくさ、不随意運動といった多様な症状が報告されていることが明記されています。しかし接種を受けるようにという過大な宣伝が行われる一方、副反応については、全くと言ってよいほど情報提供は行われていません。2010年から2013年に接種を受けた副反応被害者117人が原告となり、現在、国と製薬会社を相手に裁判が行われています。私は2013年からその被害者の多くとかかわり裁判の経過を見てきました。原告の女性たちは10代のたくさんの特別な経験ができる時期を体調不良と戦い治療に専念することで失い、今もその苦しみは続いています。この副反応に対する治療法は確立していません。ワクチンの積極勧奨が行われている今、被害を減らしたいという立場から以下質問します。
- 2022年4月にHPVワクチンの積極的勧奨が再開されてから、副反応の被害が広がっています。実際にHPVワクチン接種後の症状に対応するために国が指定した協力医療機関を新規に受信する患者が全国で急増していることが厚労省研究班の調査でわかりました。2022年4月の勧奨再開後の2年9か月間で新規受信者数は合計545人に上っており、患者数は現在も増え続けています。区はこのことをどうとらえているか、認識をうかがいます。
- 杉並区でも2022年4月以降、キャッチアップも含めて接種者が増えていると思いますが、実際に何人が接種を受けているのか、うかがいます。男子についてもお答えください。
- 厚労省が出しているワクチンについてのリーフレットには1万人に2から5人の割合で重篤な副反応が出ていると書かれていますが、実際に杉並区ではそのような報告は上がっているか、重篤でないものも含めた副反応被害についてうかがいます。また保健所に相談が来ている数および具体的な相談内容についてもうかがいます。
- 先日2022年4月以降にワクチン接種を受けた高校生が、重い副反応が出て、病院を受診するも、症状についてわかる医師がいなく、検査で異常が見つからないという理由で帰され、他の多くの病院でも治療できるところがなく、やっとのことで裁判を支援する人たちのグループに出あい、しっかり診察をしてくれる医師に治療をうけることができたとの話を聞きました。しかしそれでも体調は戻らず、視覚の異常や激しい頭痛、運動障害などによって彼女は学校を休学しているとのことです。
これまで被害者の声を聴いてきた中でもこのような事例は枚挙にいとまがなく、副反応ではないかというと、それだけで病院でひどい対応を受け、まともに取り合ってもらえず、精神科をすすめられ病院をいくつもたらいまわしになるということが起きてきました。このようなことは真に避けなければならないと考えますが、区の見解をうかがいます。
- ここで新医協(新日本医師協会)が発行している「プライマリーケア医が行うHPVワクチン副反応診療の手引き」という冊子を紹介したいと思います。冊子の冒頭にはHPVワクチン接種者の増加とともに発生した重篤な副反応問題を重視し2018年にHPVワクチン検討会を立ち上げ、原著論文の精読や患者からの症状の聞き取りを行い23回にわたる検討を経て、患者に共通する多様で重層的に現れる症状はワクチン接種を原因とした免疫学的機序による症状ではないかという結論に達したことが述べられています。一方で厚生労働省は、重篤で多様な症状について、ワクチン成分による免疫が介在する副反応の可能性などを否定し、注射を契機とする「機能性身体症状」と定義し、身体リハビリテーションと認知行動療法による治療を進めることにしました。このような基本姿勢のもとに全国に数か所の基幹病院と協力医療機関を設置しHPVワクチン接種後に生じた症状に対して診療にあたっています。
このため協力医療機関を受診した患者さんはワクチン成分の副反応ではないことを前提にして話が進められ、詐病扱いされることもあり、まともな治療が受けられないことになります。そして被害者の多くは進学や就職もままならず、日常生活も困難な状況が続いていると。自分たちは他のワクチンと比べて異様に高い発生頻度を示す重篤な副反応はHPVワクチンそのものによる副反応症状ととらえている。新たにHPVワクチン接種後に副反応症状が疑われる患者さんが受信した際に適切な初期対応を行い、地域で納得できる医療を受けられ、その後の診療支援につながることを目指してこの手引きを作成したということです。冊子は57ページにわたり、患者の事例、症状を訴えて来院した際の対応フローチャートや質問票、治療を実施している専門医療機関への紹介、地域での診療と相談の継続方法、子宮頸がんワクチン接種後の副反応の病態に関する医学的知見のレビューが掲載されており、地域の医師が被害を訴えて来院した患者を診察するにあたって、大変役に立つ内容となっています。ぜひ区は医師会を通して地域の医療者にこの冊子の紹介をしていただきたいと思いますが、区の見解をうかがいます。
- 多くのHPVワクチン副反応被害者は体に不調がでても、最初はそれがワクチンによる副反応だと気づかず、具合が悪いまま2回目、3回目を接種してさらに状態が悪化するということを経験しています。早い段階でワクチンによる副反応と気づけば追加のワクチン接種を避けられ、それ以上の悪化を防ぐことができます。小中学校の養護教諭がHPVワクチン副反応被害のことを知っていて、具合が悪くて保健室に来た生徒の状態をみて副反応かもしれないと気づき、診療につなげることは非常に重要で、被害者を守ることにつながります。これまでも、保健所が養護教諭に副反応被害について情報共有することを求め教育委員会でも対応するとの答弁をいただきましたが、どのように情報共有が行われたのか、具体的にお答えください。
- 被害者たちは2度と自分たちのようにワクチン被害によって人生を台無しにする子どもを出したくないとの強い思いで被害を知らせるリーフレットを作りました。ぜひ小中学校の養護教諭にそのリーフレットを配り、被害について知っていただきたいと思いますが、教育委員会の見解をうかがいます。
- 子宮頸がんを防ぐには検診が非常に有効です。区民の検診受診率について十歳区切りでお答えください。
- 区では検診受診率を上げるためにどのような取り組みをしているでしょうか、うかがいます。
- HPV感染は性交渉によっておこるとされています。しかしこのワクチンの対象となる小学校6年生から高校1年生までの子どもたちは性交渉について義務教育で学習する機会が保証されていません。これを知ることによって初めて、自分はワクチン接種をどうするか、受けるにしても何歳で受けるかを自分で考えて決めることができます。この知る権利を保障するためにも包括的性教育を行うべきだと考えますが、教育委員会の見解をうかがいます。
子宮頸がんを防ぐためとしてHPVワクチン接種が行われていますが、国も製薬会社も副反応被害者と真摯に向き合わず、まともな治療が受けられないという状況がずっと続いています。杉並区は接種を行う自治体として、責任を持って被害にも向き合っていくことを求めて次の項目に移ります。
外国ルーツの子どもの学習支援について質問します
杉並区内の外国人登録者数は近年増加を続け、2025年8月1日現在では24,338人で区民の約4.2%を占めるまでになっています。1年前は20.807人でしたから3,531人、17%の増加です。当然小中学校に在籍する外国ルーツの子どもの数も増え続けています。私は過去に留学生の支援団体で働き、留学生の相談を受け、課題に取り組んできました。今外国ルーツの子どもの日本語ボランティアにかかわるなかで、本人の意思とは関係なく家族に伴われて日本に連れてこられる子どもたちは、自分の意志で来日する留学生や大人とは全く違う理不尽さをかかえて、言葉が通じず友達もいない日本での暮らしをスタートさせることになり、さまざまな困難にぶつかっているようすを目の当たりにしています。子どもたちが、言葉が通じない学校で、まずは安心して生活や学習に必要な日本語を習得できるよう、支援の充実を願って以下質問いたします。
まず初めに外国ルーツの子どもの支援について、教育委員会はどのような考え方で支援を行っているのかうかがいます。子どもが日本で生活し、学校生活を送るために欠かせないのが日本語を習得することです。現在は取り出し授業が80時間を終える前にアセスメントをして必要と判断されると追加で補充指導が40時間加わり、最大で120時間の取り出し授業が行われていると認識していますが、それについて具体的にうかがっていきます。
1.80時間または120時間の取り出し授業を受けている子どもはどのぐらいの人数になるのでしょうか。今年度までの3年間の推移を伺います。国籍別ではどのようになっているか、合わせて多い順に5番目までうかがいます
2.日本語の学習支援にあたっては子どもの状況を知るアセスメントが適切に行われることが重要です。杉並区では、子どもの力をどのように測っているかうかがいます。
3.文部科学省は2025年4月に「文化的言語的に多様な背景を持つ外国人児童生徒等のためのことばの力のものさし」を公表しました。以下「ことばの力のものさし」とします。これは従来の「日本語ができる/できない」という単線的な評価を超えて、外国ルーツの子どもたちの言語力を全体的に、かつ発達段階に応じて把握できるようにつくられた新しい枠組みで「子どもが持つすべての言語を言葉の力として認める。思考・判断・表現を支える複数言語でのことばの力の発達と日本語習得の二つの軸でとらえる。こどもの成長を“見える化”して支援に活かす」という点が特徴とされています。このような新たな方法についての区の見解をうかがいます。
4.日本語指導に「ことばの力のものさし」を取り入れるにあたっては、アセスメントとして、ペーパーテストではとらえきれない子どものことばの力を一対一の対話を通してとらえようとする支援付きの評価方法、DLAを取り入れることが推奨されています。DLAを取り入れたアセスメントについての区の見解をうかがいます
5.取り出し授業を行っているのは、退職された教員の方や特に資格はないけれど、自身で日本語の教え方を学んでいる方たちで、年1回の研修が行われているとうかがっています。私はボランティア子ども日本語教室でボランティアをするにあたって、最初に20時間、その後もブラッシュアップのための研修を受けさせていただいています。その研修が大変有意義で子どもと一緒に学ぶことの助けになっています。その中でも受けて本当によかったと思ったのが地球っ子クラブ2000の高柳なな枝さんを講師に招いた研修です。子どもがおかれている状況や気持ちを理解すること、自分の姿勢を省みること、彼らを日本の学校に適応させることに一生懸命になるのではなく、多様な経験、背景を持っている子どもの成長を考えることの大切さを学ぶことができました。このような研修は学校での日本語指導者の方たちにとっても有意義で、ぜひ聴いていただきたいと思いましたがいかがかうかがいます。
6.外国ルーツの子どもの支援については、子どもに関わる大人全員で情報共有し、共同で支援していくことが大切だと思います。外国ルーツの子どもの支援の進め方等について、必要な子どもには、個別の支援計画を作って支援しているのか、また、どのように作られているのかうかがいます。
7.外国ルーツの子どもが日本語で学ぶために、授業や指導に「やさしい日本語」を取り入れることが有効だと思います。これは、外国ルーツの子どもに限らず日本人の子どもにも有効です。外国ルーツの子どもがクラスに在籍する教員には、やさしい日本語の研修を受けていただきたいと思いますが、そのような機会は設けられているのかうかがいます。
8.外国ルーツの子どもがクラスに在籍する教員や支援に関心がある教員が、日ごろの授業での工夫を教員同士で共有したり、研修を受けたりする機会があるといいと考えますが、教育委員会の考えをうかがいます。
最後に子どもたちへの母語話者による支援と母語修得のための支援の2点についてうかがいます。
9.ほとんど日本語ができない子どもにとって母語でコミュニケーションをとれる母語支援員と出会うことは、子どもが安心感を持って学校生活をスタートするために、また校内の教員やほかの支援員との間をつなぎ、外国人保護者との対応に関しても非常に有効な役割を果たすものと考えます。2024年の第2回定例会で多文化共生の推進について一般質問でとりあげ、通訳ボランティアの派遣について伺いましたが、それは母語支援に当たります。質問では通訳ボランティア制度の小中学校や保育施設への周知と予算の確保を求めたところ、周知に努めること、予算については関係課で協議していくとお答えいただきました。その後の進捗状況についてうかがいます。
10.外国ルーツの子どもにとって、母語の修得は非常に重要です。日本で生まれ育ったり、幼児期に来日する子どもほど母語喪失のリスクは高く、親の話す母語がわからないまま日本語のみで育った子どもたちが抽象的な思考ができなかったり、小学校低学年程度までの読み書きしかできないという深刻な事態も見受けられるそうです。母語が確立されている子どもほど、第2外国語として日本語を学んだ際にもその力は向上が見込めます。日本社会の中で子どもを産み育てていく過程で、保育園や学校から「子どもが日本語ができるようになるように、家の中でも日本語で会話してください」などとアドバイスを受けたことがきっかけで外国人保護者があまり得意ではない日本語での子育てに踏み切る場合があり、子どもが成長するにつれ子どもの話す日本語が理解できなくなったり、子どもに対して何が悪いのかなどの理由を日本語で説明できなくなる深刻な状況も生まれているといいます。外国人が多く在籍する愛知県では外国籍の人が自らの家庭やコミュニティ内において、子どもたちに母語や母国の文化の大切さを教えたり、母語による学習支援などの取り組みを行う際の参考にと母語教育サポートブックを作成しています。インターネットで、無料でダウンロードできるようになっていて、母語教育の重要性について理解することができます。ぜひ教育委員会、交流協会、また子ども家庭部の保育施設担当課でも参考にしていただき、日常的に顔を合わせる外国籍の人たちにこれを伝えていただきたいと思いました。区、教育委員会それぞれの考えをうかがいます。
先の参議院議員選挙では「日本人ファースト」というスローガンが注目され、それによって「外国人政策」なる言葉が登場して日本に住む外国人をめぐる議論が過熱し、差別的な言動が社会に許容される状況がつくりだされていると感じます。子どもの社会でもこの影響は大きく、実際に外国ルーツの子どもたちがいじめを受けたり、嫌な思いをすることが起こっています。子どもの権利を守るために、このような事態をなくすことは大人の責任です。これからも杉並区が掲げる多文化共生基本方針に沿って、国籍、人種等による差別や偏見のない、多様性を認め合う多文化共生社会をつくるために活動することを申し上げ一般質問を終わります。