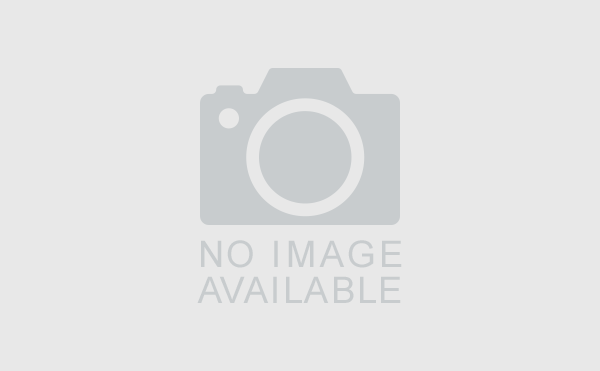区議会第3回定例会一般質問 2025.9.11 奥田雅子
シスターフッド杉並の一員として
1.「きょうだい」支援について
2.介護保険制度について
一般質問いたします。
まず、「きょうだい」支援について伺います。
「きょうだい」とは病気や障がいのある人の兄弟姉妹のことで、「きょうだい」とひらがなで表現します。特に支援が必要となる未就学から高校生までを「きょうだい児」と呼ぶこともあるようです。今年の予算特別委員会でも「きょうだい」をテーマに質問をしたところですが、区は「きょうだい」なりの困難さをきちんととらえて下さっていることが確認できた一方、「きょうだい」への支援が十分でないこともわかりました。また、障害施策では当事者にスポットを当てる場面が多くなるが家族支援にも目を向けていきたいという趣旨の答弁をいただきました。子どもが安心して健やかに成長できるよう子どもの権利に関する条例が制定された今こそ、どんな状況にあっても子どもが自分らしく生きることが保障されることが具体的に進むことを願って質問します。
ヤングケアラーがそうだったように、そこに光を当てることで施策が具体化され一歩前進していく、「きょうだい児」支援も、そんな性質の課題になるのではないかと思います。児童福祉・障害福祉分野のきょうだい支援に関する法施策について遡ってみると、2015年の児童福祉法の一部を改正する法律で小児慢性特定疾病対策の中にきょうだいの預かり支援が既に入っており、その後も放課後等デイサービスガイドラインや児童発達支援ガイドラインにも兄弟姉妹を含む家族全体の支援が盛り込まれてきました。そして、2023年4月にはこども基本法が施行され、それを基にこども大綱が12月に閣議決定され、障がい児支援・医療的ケア児等への支援という項目に保護者やきょうだいの支援を進めると受け継がれています。かれこれ国レベルでは10年前からきょうだい支援の視点はあったものの、施策化が進んでいないというのが実情ではないでしょうか。現場である地方自治体の中できょうだい支援の必要性が理解されないと、どうしても後回しにされてきたのではないかと感じています。子どもがおかれている状況は様々であり、ニーズも違うということを前提に誰もとりこぼさないためにはその実情を庁内全体で把握していくことが必要だと思います。
そこで伺いますが、
- 杉並区では様々な子どもの実態をどのように把握し、制度やサービスにつなげているのか伺います。また、つなげられる制度やサービスがない場合はどうしているのか伺います。
杉並区でもヤングケアラー支援がいよいよ具体化してきました。今後、子ども、障害、高齢、教育等の様々な分野の関係機関に研修を実施し、周囲の大人がヤングケアラーの存在に気づき負担軽減につなげることができるよう取り組んでいきますと、今年度からの杉並区子ども家庭計画にもあります。障害のある兄弟姉妹を持つ「きょうだい」の中にはヤングケアラーもいるかもしれませんが、ケアを担っていなくてもきょうだいが抱える葛藤が様々にあり、ヤングケアラーと地続きできょうだいの存在を意識していけると良いのではないかと考えます。ヤングケアラー調査でも将来への不安を語るきょうだい児の切実な声も寄せられていました。いくつか紹介すると「両親がいなくなった後誰が世話をするのか不安になる。」「弟がいるから一度も家に友達をよんだことがない。弟の障害を学校で内緒にしている。隠さずにいたかったし、友達と家で遊びたかった。」「家を離れて進学したかったのに、今は経済的に難しいし弟の将来のためにお金を貯めなくてはならないので、独り暮らしは諦めてほしいと言われた」「行政にはきょうだい児が障がいのある兄弟の面倒を見なくても大丈夫な社会のしくみを早くつくって欲しい」などとあり、きょうだいの率直な声と受け止めました。親なき後の課題ともつながっています。
- そこで伺いますが、ヤングケアラー支援に関する関係機関の研修にきょうだいという視点も盛り込んでほしいと考えます。きょうだいも相談するほどではないと思いながらモヤモヤしている場合も多いと思います。きょうだいの心理や複雑な立場について理解できるような研修を求めますがいかがか、見解を伺います。
- また、予特でも紹介した支援団体が作成しているリーフレットのようなツールの作成を検討いただけるとのことでしたが、特に子どもが相談してくるような窓口の案内にも“きょうだいの相談もできるよ”“きょうだい児が自分も対象なんだ”ということがわかるような工夫をしてはどうかと考えますがいかがか。
- 相談が来た際にきょうだいに限らない話ですが、その相談者に合った情報が提供できるように、日ごろから支援団体の発行する冊子や活動情報などを収集し、関係機関で共有するしくみが必要かと考えますが区の見解を伺います。
- 支援団体のお話ではきょうだい児支援、保護者支援、啓発の3本柱で活動を展開したいと思っても、全てを行っていくには限界もあるとのことでした。今後、区がきょうだい支援を行っていく際には、支援団体が持つ知識や経験を区と共有する中で、お互いの役割分担なども確認できると「きょうだい児」支援の継続性も担保できるのではないかと考えますが、区の見解を伺います。
- 特に学校は「きょうだい児」にとって家庭以外で一番身近に接している場所です。学校現場においても誰一人取り残さず、子どもの境遇を理解していくことはとても必要なことだと考えます。「きょうだい児」という視点を一つ先生方の意識に加えていただけたらと思いますが、教育委員会の見解を伺います。
- 練馬区や板橋区、武蔵野市などは障害者計画や子どもプランにきょうだい支援が位置付けられ、交流会などの取組を始めています。今後、杉並区の障害者施策推進計画や子ども家庭計画にもぜひ、「きょうだい」支援を加えていただきたく見解を伺います。
るる、きょうだい支援の必要性について述べて参りましたが、新たにしくみをつくるというより、今ある取組みにきょうだいという視点を加えてほしいという提案です。ぜひ前向きにご検討くださいますよう要望し、次のテーマに移ります。
- 介護保険制度について
初日に他の議員の一般質問でも取り上げられておりましたが、介護保険制度の課題は多くの区民に影響を及ぼす問題であり、私からも質問してまいります。
介護保険制度が施行されて25年。3年ごとの改定は保険料の負担増と給付抑制の繰り返しで、まるで家族介護への回帰を促しているとしか思えず、本来の目的であった「介護の社会化」はどんどん後退しています。国では次の第10期介護保険事業計画に向けた改定議論が着々とすすんでおり、私たちが知らぬうちにさらに制度の改悪がされようとしています。保険料の負担感の増大と共に、介護を担う人材の不足は深刻さを増し、「制度あってもサービスなし」という状況をこのまま見過ごして良いのか。杉並という地域で暮らす人々の人生やいのち、人権にかかわる問題に区としても主体的に向き合い、国と区が共に解決に向けた取り組みをすすめていくべきと考えます。
介護が必要になっても、住み慣れた自宅で安心して暮らせることは多くの区民が望むことだと思います。それを支えるのは在宅介護の体制であり、ケアマネや訪問・通所系の事業所は無くなっては困る存在です。杉並区においてもヘルパー不足は深刻で対策が急がれます。
- 杉並区内の訪問介護事業所数について、ここ3年間の推移を伺います。
- 介護事業所の実態把握については、現在高齢者等実態調査の中で実施していると思います。今回の調査は内容を見直し、より実態がわかるような設問にしていると認識していますが、具体的にどのように見直ししたのか初日にも答弁がありましたが、改めて確認します。
生活者ネットワークでは昨年4月の介護保険制度の報酬改定により訪問介護の基本報酬が引き下げとなったことで、訪問介護事業所の運営に与える影響について実態把握をするため、昨年7月から10月にかけて、都内22自治体で運営する介護事業所に協力を依頼し、大手損保系列事業所、社会福祉法人などを含む58事業所に対し「訪問介護事業所の運営に関する実態調査」を実施しました。
この調査から見えてきたものは、訪問介護事業所の多くが訪問介護以外の介護保険事業や介護予防と日常生活支援もふくめた総合事業及び行政からの委託事業を受けており複合的な運営を行っていること、訪問介護では身体介護を増やすことにより収入が安定していきますが、今回の調査では比較的小規模な事業所が多く、生活援助対応が多いことが分かりました。報酬単価の低い生活援助を大手事業所は受けたがりませんが、地域に根差し利用者ニーズに応えるサービスを展開している事業所は単位数の低い単体の生活援助や日常生活支援総合事業の比率が高くなる傾向にあり、結果、事業運営を厳しくしている状況が分かりました。東京商工リサーチが発表したレポートでは2024年の訪問介護事業所の倒産は過去最高の81件あり、前年度から21.1%増加しました。3年連続の倒産件数増加は人手不足や人材獲得競争の激化、物価高騰、コロナ禍のダメージ等が要因とみることができます。つまり、報酬改定以前から訪問介護事業所は大変厳しい運営状況となっており、2024年度の基本報酬の引き下げが追い打ちをかけた状況であることは明らかです。また、小規模と大規模の二極化がすすみ、介護事業運営の人件費比率で良好と言われている70%程度に対し、小規模ほど80%を超える事業所が多く、全体の36%あり、経営の硬直化がみられました。そして、なによりも深刻なのが人員不足と職員の高齢化があり、頻繁に行われる制度改正に対応することや、処遇改善加算の申請に割かれる事務量の増加も現場を苦しくしている要因となっています。利用者は今後確実に増えますが、求人倍率は約15倍と全く人が来ないなど、ヘルパーの地位向上と基本報酬アップが実現しなければ、後10年で訪問介護事業は立ち行かなり、大変危機的状況にあると言わざるを得ません。
- 私どもの調査では対象の数こそ多くはありませんが、おおよその実態は見えてきたと思います。今後区の調査でも明らかになると思いますが、生活者ネットワークで行った訪問介護事業所調査から見えてきた課題に対して、区はどのように認識したか見解を伺います。
介護保険制度は国の制度だから、基礎自治体がどうこうできないと思われがちです。1年前の一般質問でも訪問介護事業所の基本報酬が切り下げられ、窮地に追い込まれていることに対し、区は「国において介護保険制度の安定的で円滑な運営と持続可能性を確保する観点から必要な改善、見直しを図っていくべきものと認識している」という答弁でした。訪問介護事業所がなくなり、訪問介護ヘルパーがいなくなったら、区民の在宅介護を今後誰が支えるのかと、現に人手不足によりすべての依頼を受けられない事業所もあり問題は非常に深刻ですが、区の答弁は他人事のようにしか聞こえませんでした。世田谷区や品川区では独自給付に至った経緯こそ違いはあれ、区として介護事業所への直接給付を行っています。世田谷区は訪問介護事業所に88万円と特に厚く給付していますが、他の高齢・障害の居宅系事業所や入所系施設にまで対象を広げ、給付金の使途も自由とあって、給付と併行して行った事業者のアンケートからも助かるという高い評価を得ていました。
- 今議会で上程されている補正予算において、物価高騰対策として615所の介護サービス事業所に6406万2千円が計上されましたが、食材費や光熱費等の一部に対する助成であり、訪問・相談系の事業所には効果的な対策とはならないのではないかと感じました。区独自の事業者への直接給付についてどのように検討した結果、今回のような提案に至ったのか伺います。
厚生労働省によると、第9期介護保険事業計画の介護サービス見込み量から推計した介護職員の必要数は2026年度に約240万人、2040年度には約272万人となり、2022年度対比でそれぞれ+約25万人、+約57万人ということで、私が介護が必要な年齢になる頃は、めったなことでは介護は受けられないのではないかと恐ろしくなります。
また、内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によれば、65歳以上人口に占める単身世帯割合は10年後の2035年には女性が27.9%で約3.5人に1人、男性が22.3%で約4.5人に1人と推計されています。さらに、「認知症および軽度認知障害の高齢者数と有病率の将来推計」によれば認知症と軽度認知障害の有病率の合計値は2022年時点で約28%ですが、2040年には30.5%になると言われ、高齢単身者を支える訪問介護サービスの重要性はより一層高まることは明らかです。
2024年11月29日付の財政制度等審議会の建議では「訪問介護事業者は倒産もしているが、新規参入が容易で事業所数全体は増加している」と説明しています。しかし、基本報酬そのものが一般産業並みの給与を保障できる水準に引き上げられなければ、新たな人材確保も進まず、経営を維持できずに倒産を繰り返すことになるのではと危惧します。
- 区は訪問介護職員の人材確保のためにはどうすればよいと考えているのか見解を伺います。
先も触れた2024年11月29日の財政制度等審議会の建議では要介護1・2の地域支援事業への意向をめざすとしていること、ケアマネジメントの利用者負担の導入、利用者負担割合についても原則2割とすべきとしています。私は、そもそも、国における介護保険制度の議論が、本来国民の福祉にかかわる問題であるにもかかわらず、財務省が主導する財政制度等審議会で行われていることにずっと違和感を持っていますが、それらの方向性は今年末までにはまとまってくるとの情報です。
- 1年前の一般質問において総合事業についての質問に対して、区は、「現在、関係部門が連携して、事業の検証と課題の洗い出し、今後の方向性やそのための組織体制の在り方などの検証に着手したところだ」と答弁しています。要介護1・2も地域支援事業に移行するかもしれないことについても当然、その議論の中で話し合われていると推察しますが、今後の総合事業についてどのような見解になっているのか伺います。
介護サービスは生活を支える経常的な支出となる訳ですが、利用者負担割合が原則2割となることで、利用控えにつながり、その結果、重度化がすすみ家族等の介護者の負担が増大し、介護離職の増加も懸念されます。一般社団法人日本デイサービス協会が2022年度に実施した「自己負担原則2割導入における利用者意向アンケート」では回答者3018人の内の37.4%が利用を減らす等サービスの見直しを行うとあり、その理由として66%が経済的理由を挙げています。また、ケアプラン有料化についてはケアマネジメントの利用が抑制されることにもつながる懸念があり、そうなることで、要介護者の状態変化の早期発見・早期対応が困難になり社会的負担が増大するおそれがあります。そして、料金が発生した途端サービス化され、相談の入口であるソーシャルワークとしての本来の役割を損ねる懸念もあります。
- 区は利用者負担割合原則2割およびケアプラン有料化についてどのような見解をお持ちか伺います。
国は制度の持続可能性のことばかりで、高齢者の持続可能な生活という視点が欠落していると思います。この問題はどの自治体でも共通の課題だと思います。特別区長会や介護保険課長会などから東京都や国に働きかけていく動きはないのでしょうか。人々の暮らしの現場に一番近い基礎自治体は当事者やケアラー、事業者、地域の支援者などの生の声などを丁寧に聞き取り、地域の実情を把握した上で他自治体と連携し東京都や国に意見を上げていってほしいと思いますが最後に区の見解を伺って、私の一般質問を終わります。