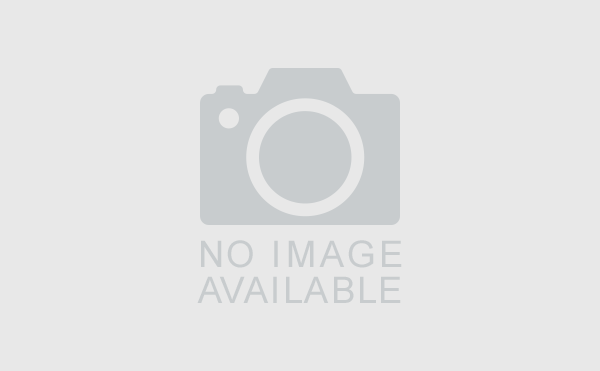区議会第1回定例会予算特別委員会まとめの意見 奥田雅子 2025.3.18
区議会生活者ネットワークを代表して、2025年度杉並区一般会計予算並びに各特別会計予算及び関連諸議案について意見を述べます。
昨年元旦に発生した能登半島地震に追い打ちをかけるように9月の容赦ない豪雨、また、14年前の東日本大震災の津波被害を受けた岩手県大船渡市で起きた山火事は鎮圧まで11日間を要し、市の面積の9%に当たる2900haを焼失、平成以降日本最大規模の山林火災となりました。度重なる災害に能登半島および大船渡の被災された方々にお見舞いを申し上げるとともに、犠牲になられた方のご冥福をお祈り致します。また、昨年8月および本年1月には宮崎県で発生した大地震により南海トラフ地震臨時情報が発表され、米の買いだめによってスーパーから米が消える騒動となりました。
夏の猛暑、冬の大雪、山火事の拡大を招いた乾燥と強風、豪雨など、いずれも気候変動が影響していることは紛れもないこととして認識する必要があります。既に農水産物の生産現場ではこれまで通りには行かない現象も現れています。円安の影響も相まって食料等の物価高騰も続いており、賃金アップが追い付いていない状況です。東京商工リサーチによると次年度に賃上げを予定する企業は85.2%でしたが中小企業ほど賃上げ率は厳しく、賃金格差は埋まらない状況です。
これらに加え、団塊の世代が全員75歳となる2025年が到来し、社会保障費の増大、労働人口の減少、インフラの老朽化など、どれも優先順位をつけがたい課題に対して難しい区政運営が迫られています。
こうした先の見えない不安定な社会状況の中、私ども生活者ネットワークは、住民に一番身近な基礎自治体の役割である区民福祉をいかに支え向上させるか、暮らしの安定と区民の命・財産を守り、子どもたちが将来に希望を持てる予算となっているか、情報公開と対話を重視し、住民自治の視点が大切にされているかに注目しました。
予算特別委員会の質疑も踏まえ、評価する点及び要望する点など意見を述べます。
先ず、最初に区財政および区政運営について
一般会計及び3つの特別会計の総予算額は3600億403万8千円で、対前年度比235億5566万円7.0%増となり、その内の一般会計は2456億300万円で対前年度比227億1100万円、10.2%増です。
区財政の状況は、社会保障費の増に加え、最低賃金の上昇等に伴う人件費やサービス委託経費等の増、また、労務単価の上昇や資材価格の高騰を踏まえ、区立施設の老朽化対応の更新経費等についても予算が見込まれています。一方、今年度新たに策定された「多文化共生基本方針」や「子どもの居場所づくり基本方針」、施設マネージメント計画などの具体化に向け、総合計画・実行計画の単年度の修正が行われました。その実現のための予算の計上や防災・防犯への備えに対する予算など、守りに入ることなく区民福祉の向上に確実に予算を計上したことは重要です。
また、「財政健全化と持続可能な財政運営を確保するための基本的な考え方」において(仮称)杉並区役所庁舎整備基金に当面20億円を積み立てることを明確にしたことも確認しました。
物価高騰や国際情勢、金融資本市場の変動等、依然として先行き不透明な状況ではありますが、健全で持続可能な財政運営に努めていただくようお願いいたします。
ここからは総合計画施策体系に沿って個別テーマに対する意見を述べていきます。
第一に防災・防犯について
防災・防犯用品カタログギフトの配布については多くの批判も出されました。しかし、単にカタログから選んで終わりではなく、カタログ自体が区の防災・防犯対策の情報発信ツールとなると理解しました。杉並区に特化した情報を充実させるとともに、いざ発災したら何が起こるかがイメージできるものであることや、この配布事業に込めた区長のメッセージ動画をリンクさせるなど、一人でも多くの区民に活用してもらうための工夫を検討するよう求めます。
第二に街づくり・地域産業について
誰にとっても移動しやすい地域交通環境の整備では移動不便地域での課題解決に向けて行われる堀ノ内・松ノ木地区周辺でのAIオンデマンド交通の実証実験に期待するところです。地域住民がより使いやすい移動手段となるよう、利用者の声も聴きながら丁寧にすすめていただくよう要望します。
住宅施策の推進では住宅確保要配慮者の住まいの確保が確実にされ、その後の日常生活支援も含めた居住支援の仕組みづくりを着実に進めていただくよう求めます。また、新たに始まる家賃助成制度も含む、様々な情報をわかりいやすくまとめ、不動産事業者や要配慮者を支援する団体などと共有し、必要な方に情報が届くよう進めていただくことを要望します。
多面的機能を有する都市農地の保全に学校給食の食材利用が効果を果たすようになることが重要です。年2回の地元野菜デーを日常の取組となるようなしくみづくりに期待しています。
第三に環境・みどりについて
気候危機問題はすべての人に関わる問題であり、再生可能エネルギーの拡充と断熱の推進は両輪で進めていくことが必要です。気候区民会議の議論を通してまとめられた様々な区民アイデアを事業化につなげ、引き続き区民参加型の取組で気候変動対策を推進していくことを期待しています。
羽毛ふとんや羽毛製品のリサイクルに取り組むことを評価します。区民への周知および回収拠点の拡充を検討していただくよう要望します。
グリーンインフラの推進やみどりの基本計画改定を区民参加でと提案してきたものとして、それがいずれも取組につながったことを大いに評価します。みどりの基本計画の改定が遅れていることをプラスに捉え、幅広い分野での議論がなされることを期待しています。
新たにつくられるグランドに人工芝を敷くことについて取り上げました。人工芝はマイクロプラスチックの最大の排出源になっていて、それを体内に取り入れることの健康影響についての研究も進む中、今後、区全体の人工芝についての考え方を見直すよう求めます。
第四に健康・医療について
費用対効果が悪く国が定期接種化を見送った、男性へのHPVワクチン接種助成が始まってしまいます。副反応疑い報告の頻度が他の定期接種に比べて8倍以上も高く、約120人が全国で薬害の裁判を争っているワクチンです。接種希望者にはしっかりとデメリットの情報を伝えることを求めます。区が想定する男性の接種希望者は298人とのことで、健康被害が疑われる際に適切な対応がとれるよう、小中学校の養護教諭に情報提供を行うことを求めます。
第五に福祉・地域共生について
男女共同参画の推進では今年の1月に「杉並区ジェンダー平等に関する審議会」が設置され、杉並区のジェンダー平等の施策が充実することを期待します。
高齢者の在宅生活を支える要となる訪問介護の報酬単価が切り下げられ、元々人材不足に苦しむ地域に根差した訪問介護事業所はさらに窮地に追い込まれています。独居高齢者が増える中、公的サービスとインフォーマルなサービスを組み合わせて包括的に高齢者を支える体制の構築が急務です。また、新たな認知症観に基づく認知症本人およびケアラ支援の充実についてもしっかりと取り組んでいただくことを要望します。
障害児童の移動支援事業において学校および自宅と放課後等デイサービス事業所間で利用できるように早期の見直しに期待します。
又、今年度から合理的配慮が民間事業者にも義務付けられたことを受け、共生社会しかけ隊の取組に期待します。
第六に子どもについて
子どもの居場所づくり基本方針が策定され、現在残る25館の児童館の存置が打ち出され、さらに児童館のない中学校区に7館が、さらに7地域に1館の中高校生機能優先館が設置される方針を確認しました。また、様々な区立施設を活用した子どもの居場所の創出で、子ども自らがその日の気分で選べる環境が整うことは重要です。
障がい児支援の充実と医療的ケア児支援体制の整備が進むことを期待するとともに、障がいの兄弟姉妹を持つ「きょうだい児」支援についても目を向けていただくよう要望します。
児童相談所の設置準備を着実に進めていることが確認できました。児童虐待の早期発見・未然防止の強化、要支援家庭を対象とした事業の充実、子どもイブニングステイの実施など、すべて子どものいのちを守る重要な取り組みです。新規事業として、社会的養護自立支援拠点事業の準備が盛り込まれたことで、誰一人取り残さない取り組みが進むことを期待します。
第七に学びについて
学校を取り巻く環境が複雑化、多様化する中、教員の負担が増しているため、新たにエデュケーション・アシスタントを小学校全校に1名ずつ、導入されることが示されました。教員の負担軽減がはかられ、授業の質が向上することに期待します。
教育相談体制を充実するにあたって、スクールソーシャルワーカーは経験年数のバランスをとって配置ができるよう、改めて処遇の改善を求めます。
不登校対策の推進について、保護者の会がボランティアで続けてきた必要な活動を教育委員会が主体となって引き継ぐことはこれまで要望してきたことであり、評価します。不登校及び不登校傾向にある子どものために、各学校に居場所としての別室が作られることは重要です。そこに配置されるボランティアの支援員については不登校を理解するための研修を行うことを求めます。
改定された特別支援教育推進計画では、通常学級における特別支援教育推進の仕組みが強化され、これまで求めてきた作業療法士の巡回訪問などが取り入れられたことを評価します。これらの仕組みを充実させ、障がい児が通常学級を選びやすくなることを期待します。
区内中学校の総合的な学習の時間に性的少数当事者の講師が授業を行ったことが取り上げられていました。
そのような授業は、性の多様性への理解を深め、すべての人が尊重される社会をつくることに寄与するものです。区の取り組みを推進するために、教育委員会には学校がこのような授業を行うためのサポートをお願いしたいと思います。議会で取り上げられたことで委縮することなく今後も取り組みを進めることを要望します。
第八に文化・スポーツについて
外国籍の区民が増えている中で、「すべての区民が人権を尊重し、互いの文化を認め合い、安心して暮らせる地域づくり」を目標として、新たに多文化共生基本方針が作られたことを評価します。これを基に互いを尊重し合える意識の啓発、やさしい日本語の普及によるコミュニケーション支援、多文化共生拠点の整備が進み、真の共生社会づくりが進むことを期待しています。
第九に協働推進計画の取組について
これまで地域課ですすめてきた協働提案制度を見直し、公民連携を推進するための新たな仕組みを検討するにあたり、区と地域団体等による課題解決に向けて、多様な主体との連携も促しながら進めることは重要です。公民連携プラットフォームを使ってすすめようとしている区の考えも確認できました。新たな協働の在り方の検討にはNPOやボランティア団体など、地域で活動する団体の声を聴きながらすすめていただくことを要望します。
第十にデジタル化推進計画の取組について
行政手続きをはじめ、様々な分野でデジタル化による区民サービスの利便性向上、
職員の働き方改革に資するものとして必要な取組だと理解しています。さらにデジタルデバイドに対して相談窓口を設置するという配慮を歓迎するものですが、地域区民センター3か所巡回による実施については常設ではないため、わかりやすい広報に努めていただくとともに、今後、効果検証を要望します。
最後に、善福寺川上流地下調節池計画ついて、疑問を投げかける住民団体より3/12付の要望書が区長宛てに提出されたところです。私共からも区民生活に多大な影響を及ぼすことから、以下3点の要望を付して意見いたします。
まず、1点、今年2月のオープンハウスでは費用便益比B/Cが1.41と示されたものの、それは神田川流域河川整備計画全体のB/Cであり、その一部であるが独立した事業である善福寺川上流地下調節池単独のB/Cは示されていません。計画全体を構成する事業ごとのB/Cを示すことはその事業が効果的かどうかを判断するために必要不可欠です。都市工学の専門家による検討では善福寺川上流地下調節池のB/Cは0.6程度と推計され、これは費用に見合った効果は見込めない値です。善福寺川流域に時間65mmの降雨があった場合の仮想的な被害状況など、費用便益比算定に必要なデータとともにB/Cがどれほどになるかを示すこと。
2点目として、今回の地下調節池は、その大半が武蔵野市の下水道による雨水排水を受け入れるための計画といえます。区は、武蔵野市としっかりと協議連携して、ともに大雨時の災害対策に取り組むとともに、武蔵野市下水道からの流入による区内での溢水被害の防止にはならない恐れがある等、現計画が区民のためにならないことから再検討すること。
3点目、説明会の持ち方として、オープンハウス形式ではなく質疑応答の時間を十分にとり、質問者の意見を参加者が共有しながら議論が深まるような集会形式の説明会を開催すること。
以上3点、および住民からの要望に対し誠意ある回答を東京都に強く求めていただくよう要望します。
以上申し上げ、議案第28号~31号、2025年度一般会計予算および各特別会計予算について賛成いたします。
次に予算関連議案について意見を申し述べます。
議案第19号杉並区子どもの権利に関する条例について、本条例の制定は私たち生活者ネットワークの長年の願いであり、この間の審議会での取り組みでは区の本気度がひしひしと伝わってきて、毎回安心して審議の行方を見守ることができました。
今後は多くの区民や子どもたちが、子どもの権利について学ぶ機会を作り、理解がすすむことを期待します。
また条例に基づく救済機関の設置など、着実にすすめていけるよう、私たちも注力してまいります。議案には賛成いたします。
次に議案第22号杉並区いじめの防止等に関する条例について、子どもの権利条例と共に子どもを守る取り組みとして策定されることは重要です。
条例ではいじめを防ぐための学校や保護者、区民等の役割、いじめ防止等のための基本方針、いじめ問題対策委員会の設置など必要な事項を定めています。
いじめを受けた子どもを守ることは前提とした上で、いじめを行った子どもと保護者へのケアも盛り込まれたことを評価し、議案には賛成いたします
他、第16号~18号、議案第20・21,37・38号についても賛成いたします。
結びに当たり、資料作成に御尽力いただいた職員の皆様に感謝を申し上げ、区議会生活者ネットワークの意見開陳といたします。