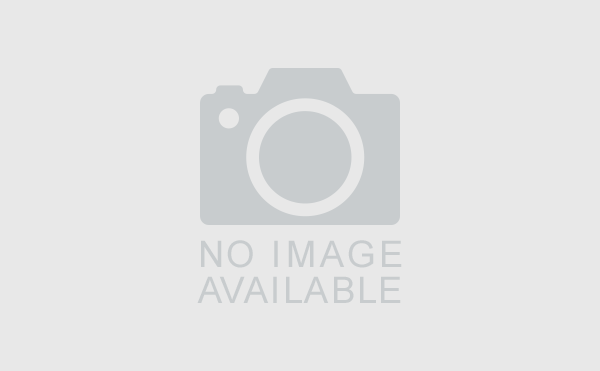第4回定例会一般質問と答弁 2025.11.21 そね文子
Q1 こんにち、包括的性教育の重要性については、多くの識者が指摘しているが、区教育委員会はどのように捉えているか見解を伺う。
A1 教育長)包括的性教育を学校教育で行う意義としては、第1に正しい知識を早期に身に着けることで性感染症や望まない妊娠の予防など子どもの心身の健康を守ること、第2に性に関する多様性や他者の尊厳を学ぶことで人権尊重の精神を育むこと、第3に自分の体や感情を理解することで自己決定力が向上すること、第4に性的虐待やハラスメントを防ぐための知識と対応力を身につけることが考えられる。学習指導要領に基づいた性に関する指導に加えて、児童・生徒を取り巻く環境の変化を踏まえた性に関する指導の必要性を感じている。
Q2 区教育委員会の性教育の実態について伺う。学校教育における性教育は、学習指導要領にもとづき、特定の学科ではなく、さまざまな教科において実施されていると思うが、どの教科でどのような内容について年間何時間行われているのか。就学前、小学校低学年、同高学年、中学校それぞれについて概略を伺う。
A2 教育委員会事務局次長)学習指導要領に基づいた性教育の実施概要は子供園では「自分の体に大切なところがあることを知るとともに、相手の体も大切にする」ことについて、プール活動の事前指導や毎月実施する身体測定の着替えの時など日常の教育活動時に指導している。
小中学校では道徳科、総合的な学習の時間、特別活動で指導している。加えて小学校低学年では生活科、高学年では理科と体育科、中学校では社会科、理科、家庭科、保健体育科で広く扱い指導している。主に保険領域と命の安全教育や理科で熱く内容では低学年では「自分の体を大切にする」など3~5時間程度、高学年では「思春期の体の変化」や「生命の誕生」についての理解など6~8時間、中学校では「身体機能や生殖にかかわる機能の成熟」「妊娠・出産のしくみ」「感染症の予防」など7~10時間である。高学年と中学校のいのちの安全教育では「性暴力の被害にあった特に適切に対応する力」が含まれている。
Q3 杉並区においても、そのような性教育の実績があると思うが、区教育委員会が把握しているのは、どのような事例か。授業の実践者、主催者(学校、PTA、保護者の有志、地域など)、授業の対象(子どもの学齢など)、授業を受けた人数、授業の内容、できれば授業後の子どもの感想なども分かれば例を挙げていただきたい。
A3 教育委員会事務局次長)学校が助産婦を招聘して中学3年生を対象に、自分や相手の命を大切にするための行動を考えるないようで実施したものがある。生徒の感想は「自分の欲求だけで行動するのではなく、相手の気持ちを考えて関わっていきたい」というものがあった。専門的な知識のある外部講師の授業は児童・生徒にとって良い学びになると考える。
Q4 包括的性教育のすぐれた取り組みが、他の学校でも行われるよう、情報が広く共有されることが望ましいと考えるがいかがか伺う。
A4 教育委員会事務局次長)他校で実施された包括的性教育の取り組みが共有されることは新たに実施を検討している学校にとって有益と考えるので、外部講師や授業内容、実施方法について必要とする学校に情報提供している。
Q5 このような取り組みは、区内のすべての学校で行われるべきであり、本来、回数を重ねることによって、内容を深めていくことが望ましいと考える。先ほど述べたように、日本の性教育に充てる時間はあまりにも少ない。区教育委員会の認識はいかがか。
A5 教育委員会事務局次長) 学習指導要領、いのちの安全教育の手引き、東京都教育委員会作成の「性教育の手引き」に基づき、学年の発達段階に応じて定められた時間数で指導している。
Q6 性教育は、就学前の子どもにとっても必要不可欠な学びであると考える。幼児がそれとは認識せずに性的な行為に及ぶことは珍しいことではなく、幼児でもその年齢なりの学びが重要だと言われている。区の認識を伺う。
A6 教育委員会事務局次長)就学前の子どもの性教育については、幼児の年齢に応じた性教育を行うことは子どもの安全を守り健やかな成長を育むために重要であると考える。プライベートゾーンの理解や「いや」と言える力を身につけることは性暴力の予防と健全な人間関係の基礎作りにつながるものと認識している。
Q7 不登校の子どもも対象から外すわけにはいかない。令和6年度、区内には1,034人の不登校の子どもがおり、子どもの権利保障を定めた杉並区子どもの権利に関する条例にてらして、子どもの学ぶ権利を守る責務があると考えるが、区教育委員会の認識はいかがか伺う。
A7 教育委員会事務局次長)性に関する教育に限らず、不登校児童・生徒が学びたいと思ったときにそのことを学べる環境を可能な限り整えることは大切だと考える。不登校児童・生徒への性に関する教育についても他の学習内容と同様に情報提供している。
Q8 性の学びは大人にとっても必要ではないか。家庭内で子どもから「赤ちゃんはどこからくるの?」と聞かれて、返答に戸惑う保護者を支援する意味からも、成人に向けた性教育は必要と考えるがいかがか。
A8 学校整備・支援担当部長)区教育委員会では、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者の学習機会の場として家庭教育講座を企画実施している。性教育は保護者の関心が高いテーマのひとつであることから定期的に家庭教育委講座の中で取り上げてきた。保護者が子どもの発達段階に応じて適切に対処できるように講座内容の充実に努めていく。
Q9 最近、子どもを対象とする教師の性加害事件が頻発し、保護者の不安は大きい。子どもから性被害を打ち明けられたときに、そんな時間になぜそんな場所にいたのか、とか、そんな恰好をしているのが悪いというような発言で2次被害を起こさないためにも教師に向けた研修も必要と考えるが、見解を伺う。
A9 教育委員会事務局次長)教員が児童・生徒から相談を受ける場合には、児童・生徒に寄り添い需要的な態度で傾聴することを基本にしている。教員が自身の言動について振り返る機会は大切であるので、教育相談コーディネーター連絡会や生活指導主任会などで、性被害を含め子どもからの相談への対応の仕方について確認し、各学校での研修等に行かせるよう努める。
Q10 これらのことを総合的に解決するには、2027年の学習指導要領改訂のおりに「はどめ規定」を撤廃し、包括的性教育の推進を盛り込む必要があると考える。区教育委員会の認識はいかがか見解を伺う。
A10 教育長)現在学校現場では学習指導要領の「性行為は取り扱わない」という趣旨の制約や「保護者の理解」「文化的配慮」を指摘する一部の声があり、避妊方法などの具体的指導は慎重に扱う傾向があります。包括的性教育の導入は、学習指導要領が示す「心身の健康保持」「生命尊重」「発達段階に応じた指導」という基本方針と整合しており、その充実に資するものと考える。包括的性教育については、国の検討結果の如何によらず、それぞれの地域の実情や子どもの実態に応じて、学校運営委協議会や保護者の意見を十分尊重し、各校の工夫の中で取り組んでいくものである。区教育委員会はこの各校の取り組みを積極的に支援していく。