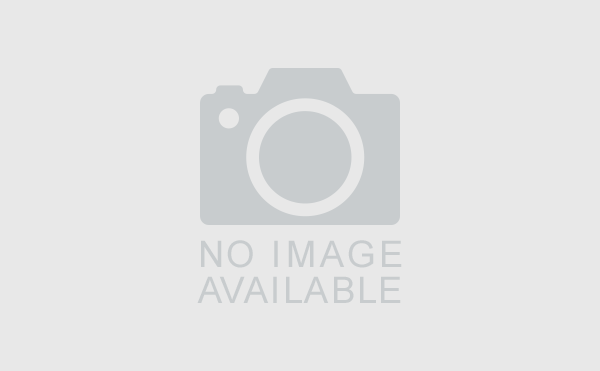第4回定例会一般質問 2025 11.21 そね文子
私はシスターフッド杉並の一員として、包括的性教育について一般質問いたします。
昨今、子どもに対する性暴力や子どもの性が消費される事件が多発しています。近親者による性的虐待や性的な目的による盗撮、撮影した子どもの性的な画像や動画が売買されるなど、報道される実態に言葉を失います。低年齢の妊娠も少なくありません。厚労省の2022年度衛生行政報告例によると、毎年20歳未満の女性が1年間に人工妊娠中絶の手術を受けるのは約1万人、1日に換算すると約336人、都内だけで約67人の手術が毎日実施されています。
SNSが急激に普及拡大する社会状況にあって、子どもが被害者になるばかりか、インターネットを介して性加害者になるケースも増えています。重大ないじめ事件には性的な暴力がひそんでいる割合が非常に高いと言われ、杉並区が事件の現場になっても不思議はありません。性的加害は「魂の殺人」と言われますが、子どもの自己肯定感を低下させて希死念慮を高め、その後の人生に長く深い傷跡を残します。
私は18歳までの子どもの声を受けとめ・よりそう活動に10年以上関わっていますが、子どもからの「性」に関する相談はたいへん多いと実感しています。子どもたちは「性」に関する知識不足から不安を抱え、SNSなどネット環境を通したフェイク情報に基づき苦悩や困惑の声を寄せてきます。なかには深刻な状況に陥っている子どももいます。子どもを被害者にも加害者にもさせないための対策は急務ですが、犯罪防止策としての加害者への厳罰化やSNSの規制、監視の強化などは、子どもが当事者の場合には必ず何らかのリスクを伴ううえ、本質的な解決とは言えません。
子どもの状況から明らかなのは、学校教育における圧倒的な「性教育の不足」です。いまの情報過多の世の中にありながら、正しい知識を身につけられないために不幸な状況を生んでいる事実を教育行政は真摯に受け止め、解決策に取り組まなければなりません。日本における性教育の貧しさは悲惨というしかなく、質・量ともに世界的に大きく後れを取っています。
この現状に危機感をもって解決に取り組む多くの教育者や専門家が提唱するのが「包括的性教育」の推進です。科学的かつ人権に基づいた、まっとうな性教育「包括的性教育」の指針として、ユネスコがまとめた「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」が、国際的に認められています。
「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」とは、国連教育科学文化機関(ユネスコ)が、世界保健機関(WHO)や国連児童基金(ユニセフ)などの協力によって2009年に作成した性教育の手引書です。その後、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」の中に健康と福祉(目標3)、質の高い教育(目標4)、ジェンダー平等(目標5)が示されたことを受けて2018年に改訂され、これらの目標達成のための手法として「包括的性教育」が位置づけられました。改訂にあたっては、SDGs以外にも世界人権宣言、子どもの権利条約、経済的・社会的および文化的権利に関する国際規約、女性差別撤廃条約、障害のある人の権利に関する条約など、人権に関する多くの国際的な理念を基盤としました。
国際セクシュアリティ教育ガイダンスが推奨する性教育は、次にあげる10項目で説明されます。科学的に正確であること、徐々に進展すること、年齢・成長に即していること、カリキュラムベースであること、包括的であること、人権的アプローチに基づいていること、ジェンダー平等を基盤にしていること、文化的関係と状況に適応させること、変化をもたらすこと、そして、健康的な選択のためのライフスキルを発達させること、以上です。
ここで示された「包括的性教育」こそが、子どもを性の被害者にも加害者にもさせないための、唯一の解決方法だと考えます。しかもリスクはゼロです。昨日は区長から、包括的性教育の重要性と有効性、そして福祉の現場に身を置く女性相談員から困難な状況に置かれる女性を減らすために包括的性教育を取り入れることを求める声があることが紹介され、とても心強く思ったところです。杉並区において包括的性教育が実践されることを願い、以下、質問します。
- こんにち、包括的性教育の重要性については、多くの識者が指摘していますが、区はどのようにとらえておられるか、見解をうかがいます。
文科省は2023年度より「生命(いのち)の安全教育」を導入し、就学前の幼児から小・中・高校生までを対象に性暴力を防止するための学びを取り入れています。杉並区でも、すべての子供園、小中学校で実施されていると承知していますが、「性」を肯定的にとらえる視点が乏しく、具体的に性の知識が学べるような内容とは異なります。文科省がこれを「性教育」と呼んでいないのは、「性教育」に位置付かないということだと認識していますが、区では「性」の学びも実施されています。
- そこで、区の性教育の実態についてうかがいます。学校教育における性教育は学習指導要領にもとづき、特定の学科ではなく、さまざまな教科において実施されていると思いますが、どの教科で、どのような内容について、年間何時間行われているのか。就学前、小学校低学年、同高学年、中学校それぞれについて、概略をうかがいます。
ある教育者の調査によると、日本の中学校での性教育の時間数は、平均で3年間の合計が8.62時間、1年間では3時間弱であり、スウェーデンの年間20時間、オランダの小学校で1シーズン8回から10回の授業、フィンランドの中学校で1年間17時間、韓国で年間15時間と言います。日本の性教育にあてる時間の少なさは際立っています。
また内容について、文科省の学習指導要領では「思春期の体の変化」「妊娠の成立」「性病予防」などを学ぶことになっている一方、「妊娠に至る過程まで」とされて性行為や避妊法の具体的な説明には触れません。これがいわゆる「はどめ規定」で、文科省は「性交について、個別指導で教えることは可能」としていますが、現場では「性交を教えない規定」と捉えられています。性の多様性(LGBTQプラス)や性的同意、性暴力などは、指導内容に明確に含まれず、基本的人権・子どもの権利の視点に欠け、包括的な学びはぜい弱と言わざるを得ません。
このように、国が定めた性教育のカリキュラムは貧弱であり、「はどめ規定」という制限によって現場は萎縮を余儀なくされていますが、そのようななかにあっても、教育現場では意欲的な授業が実践されてきました。助産師や産婦人科医、小児科医などの医療関係者、養護教諭や保健体育科の教師、性的マイノリティー支援や性暴力被害者の支援に取り組むNPOなどによって、人権に基づく包括的な性教育が一部では行われてきたと認識しています。
- 杉並区においてもそのような性教育の実績があります。区が把握しているのはどのような事例か。授業の実践者、主催者(学校、PTA、保護者の有志、地域など)、授業の対象となった子どもの学齢など、授業を受けた人数、授業の内容、できれば授業後の子どもの感想などもわかれば、例を挙げてください。
- そして、そのような授業について区としての評価はいかがか、うかがいます。
- 包括的性教育のすぐれた取り組みが他の学校でも行われるよう、情報がひろく共有されることが望ましいと考えますが、いかがか、うかがいます。
- このような取り組みは区内のすべての学校で行われるべきであり、本来、回数を重ねることによって内容を深めていくことが望ましいと考えます。先ほど述べたように日本の性教育にあてる時間はあまりにも少ない状況です。区の認識はいかがか、うかがいます。
- 性教育は就学前の子どもにとっても、必要不可欠な学びであると考えます。幼児がそれとは認識せずに性的な行為におよび、ときには他の子どもを傷つけてしまうことは珍しいことではなく、幼児でもその年齢なりの学びが重要だと言われています。区の認識をうかがいます。
- 不登校の子どもも対象から外すわけにいきません。区内にはすでに1,034人の不登校の子どもがおり、子どもの権利保障を定めた杉並区子どもの権利に関する条例にてらして、子どもの学ぶ権利を守る責務があると考えますが区の認識はいかがでしょうか、うかがいます。
- さらに、性の学びはおとなにとっても必要ではないでしょうか。親やきょうだいなど近親者による性的虐待を防ぐためにも、家庭内で子どもから「あかちゃんはどこからくるの?」と聞かれて返答に戸惑う保護者を支援する意味からも、成人に向けた性教育は必要と考えますがいかがか、うかがいます。
- 最近、子どもを対象とする教師の性犯罪事件が頻発し、保護者は大きな衝撃を受けています。子どもにとって安全であるべき学校で子どもを相手に性犯罪をおかすような教師は論外ですが、子どもから性被害を打ち明けられたときに、そんな時間になぜそんな場所にいたのか、とかそんな恰好をしているのが悪いというような教師の発言で2次被害をおこさないためにも、教師に向けた研修も必要と考えます。見解をうかがいます。
- これらのことを総合的に解決するには、2027年の学習指導要領改訂の際に「はどめ規定」を撤廃し、包括的性教育の推進を盛り込む必要があると考えます。区の認識はいかがか。見解をうかがいます。
「性」の学びは、人が幸福に健康に生きていくために必要な「人権」の学びであり、決して「性交」「生殖」だけのことではありません。忌まわしいものでも避けるべきものでもなく、多様性を受け入れ、自己決定力を育てるものです。包括的性教育を学んだ子どもは自己肯定感が高まり、初めて性交を行うにあたり慎重になることは、実践者の多くが証言し、また海外でも知られた事実です。
都内の公立中学で長年包括的性教育の授業に取り組んできた保健体育の教師も、同じく包括的性教育を埼玉県で実践してきた養護教諭も、授業の回数を重ねるにつれ子どもたちが真剣なまなざしを向けるようになり、明らかに成長を見せると言います。反社会的な行動や人権を無視した行動が激減すると言い、校長は「子どもたちが優しくなった」と感想を寄せ、校長自身も変わったと自覚したそうです。学校で一律に授業として実施することの意味がここにあります。
私は、本来、包括的性教育を推進する根拠となるような法律が必要と考えます。教育機会確保法が制定されたことで不登校の子どもの学びが保障されるベースができたように、いじめ防止対策推進法ができたことで、いじめが起きないよう防止策や、いじめが起きた場合に子どもを守るしくみの策定が義務付けられたように、包括的性教育が全国どこの学校でも平等に、格差なく、義務教育の学習カリキュラムに位置づけられ、教える側の教師たちにスキルが身につくように教職課程に盛り込まれ、そのための予算が担保されるような公的基盤として、法律が定められることが必要だと思います。同様に考える専門家や市民の団体が法整備を求めて動き出しています。私たちもこの動きに連帯し、豊かな学びが実現するよう、活動をひろげていくことを申し上げ、質問を終わります。
再質問
昨日区長は、若年女性の抱える困難に対する区の支援について答弁する中で、若年女性が困難に陥るのを未然に防ぐためには、早期の教育的アプローチも重要であること。性に関する正しい知識と自己決定権を理解する力を育む包括的性教育は、人権を考える上での重要な柱であり、暴力や搾取から自分を守る力を養うものということ。女性相談員からも一貫して福祉事務所に来なくて良い状況を作るためにこそ包括的性教育が必要と言う意見が寄せられいて、若年女性の困難の予防に大きな効果があると考えることを述べられました。
この福祉の現場の相談員からの重要な意見は教育委員会にこれまで共有されていたのかうかがいます。
役所の中では包括的性教育について職員間で自主的に学ぶ場が作られているということも伺っています。このように包括的性教育に対する明確な考えを持っている区長部局が教育委員会での取り組みを応援し、ともに前に進めていってほしいと思いますが区長の見解をうかがいます。
包括的性教育を進めることで困難な状況に陥らずにすむ人がいるのなら、ためらわずに取り組むべきだし、そのような姿勢を応援したいと思います。期待を込めて答弁を求めます。