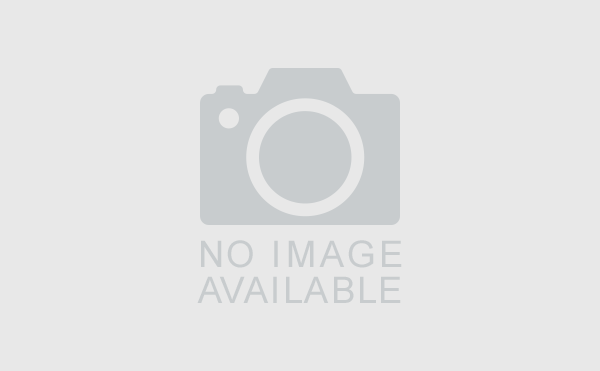第3回定例会一般質問と答弁 2025.9.11 そね文子
1.HPV(子宮頸がん)ワクチンの薬害から区民を守る取り組みについて
Q1.2022年4月にHPVワクチンの積極的勧奨が再開されてから被害が広がっている。このことを区はどうとらえているのか伺う。
A1.杉並保健所長)積極的勧奨が再開されてからの副反応の増加に対しては、接種者が増えることに伴い副反応が増加するのは想定の範囲内と考える。国は積極的勧奨の再開にあたり「HPVワクチン接種後に症状を呈した患者のサーベイランス調査」を開始し、HPVワクチン接種後に生じた症状がある患者がかかりつけ医の診察を経て受信する協力医療機関の受診者数を調査している。本調査の結果については2024年7月29日開催の102回厚生科学審議会において報告されており、国は「積極的勧奨前の2022年3月時点と比べて、再開後はワクチン接種数の増加にあわせて新規患者の増加は認められたが、全体を通して新規・継続受診者数のいずれにも顕著な変化は認められない」と見解を示している。
Q1-2.杉並区でも2022年4月以降キャッチアップも含めて接種者が増えていると思うが、実際に何人が接種を受けているのか、男子についても伺う。
A1-2.杉並保健所長)2022年4月から2025年7月までの接種者は、キャッチアップも含めて女子は13,139人だった。男子は本年4月より接種費用に係る助成を開始しており助成を利用した接種者は54人だ。
Q1-3.厚労省が出しているワクチンについてのリーフレットには、1万人に2~5人の割合で重篤な副反応が出ていると書かれているが、杉並区ではそのような報告はあがっているか。重篤でないものも含めた副反応被害について伺う。また、保健所に相談が来ている数および具体的な相談内容についても伺う。
A1-3.杉並保健所長)保健所に寄せられた相談は2022年4月以降8人から延べ9件あり、内容は健康被害救済についての質問が1件、嘔吐下痢が2件、口内炎が1件、体の痛みが3件、発熱が1件、接種個所の痛み・皮膚の隆起が1件だった。副反応疑いの報告はない。
Q1-4.2022年4月以降にワクチン接種を受けた高校生が、重い副反応が出て病院を受診するも、病院をたらいまわしされ、視覚の異常や激しい頭痛、運動障害などで休学していると聞いた。このようなことは真に避けなければならないと考えるが区の見解を問う。
A1-4.保健所長)予防接種は基本的に健康な人が免疫をつけるために受けるものであり、健康被害が出ないように可能な限り安全に実施されるべきである。万が一患者が重い副反応を訴える場合は医療機関が必要に応じ協力医療機関や専門医療機関を紹介するなど、切れ目なく適切な医療が提供される必要がある。厚生労働省のホームページには、HPVワクチンに関する情報をまとめた医療従事者向けのパンフレットが掲載されており、接種後に生じうる様々な症状のほか、必要に応じ協力機関等を紹介し、患者の行き場がなくなる状況とならないよう責任をもって診療にあたることなどが記載されている。区は公式ホームページにリンクを掲載して医療機関に情報提供するなど努めている。今後も患者が切れ目なく適切な医療を受けられるよう様々な機会を通して医療機関に周知していく。
Q1-5.新日本医師協会が発行している「プライマリーケア医が行うHPVワクチン副反応診療の手引き」という冊子を紹介したい。地域の医師が被害を訴えて来院した患者を診察するにあたってとても役立つ内容になっている。区は医師会を通じて地域の医療者にこの冊子を紹介してもらいたいと思うがいかがか。
A1-5.杉並保健所長)HPVワクチン接種後の症状が生じた患者の対応については、国が「HPVワクチン接種後に生じた症状に対する診療の手引き」を示しており、今後もこの手引き等を活用して情報提供していく。
Q1-6.小中学校の養護教諭がHPVワクチン副反応被害のことを知っていて、保健室に来た生徒の状態を見て副反応かもしれないと気づき診療につなげることは非常に重要で被害者を守ることにつながる。これまでどのように情報共有が行われたのか伺う。
A1-6.保健所長)区では学校医、産婦人科医、学校長、養護教諭、PTA代表等が参加する学校保健連絡会を定期的に開催している。HPVワクチンについては接種後に腫れや発熱が生じる場合があるほか、まれに重いアレルギー症状や神経系の症状が起きることがあることなど副反応を含めて情報共有してきた。今後も引き続き情報共有に努める。
Q1-7.被害者たちはワクチン被害によって人生を台無しにする子どもを出したくないとの強い思いで、被害を知らせるリーフレットを作った。小中学校の養護教諭にリーフレットを配り、被害について知ってもらいたいと思うが教育委員会の見解を問う
A1-7.教育委員会事務局次長)接種対象に小中学校の児童・生徒が含まれることから、養護教諭対象の連絡会で情報提供することを検討する。
Q1-8.子宮頸がんを防ぐには検診が非常に有効である。区民の検診受診率について10歳区切りで教えてほしい。
A1-8.杉並保健所長)子宮頸がん検診の受診率については、令和6年度20歳代が21.5%、30歳代が8.6%、40歳代が10.6%、50歳代が11.7%、60歳代が15.5%、70歳以上が7.3%である。
Q1-9.区では検診受診率を上げるためにどのような取り組みをしているのか。
A1-9.杉並保健所長)子宮頸がん検診の対象は20歳以上となっており、これまでは30歳以上に送付する区民検診の案内に子宮頸がん検診の受診券を同封して勧奨を行ってきた。令和6年度からは子宮頸がんの罹患率が上昇する20歳代に検診を受けてもらい、さらにその後の定期的な受診につながるよう、20歳代の全女性区民に受診券を送付し勧奨している。また、広報媒体による周知啓発にも取り組み令和6年度の受診者数は前年度の14,316人から16,520人に増加した。
Q1-10.HPV感染は性交渉によって起こるとされているが、性交渉について義務教育で学習する機会が保証されていない。これを知ることによってはじめて、自分はワクチン接種をどうするか、受けるにしても何歳で受けるかを考えて決めることができる。この知る権利を保障するためにも包括的性教育を行うべきだが、区と教育委員会の見解を問う。
A1-10.教育長)教育委員会では、学習指導要領に基づいた性に関する指導に加えて、児童・生徒を取り巻く環境の変化等を踏まえた指導の必要性を感じているところだ。今年度は東京都教育委員会が設定した「性教育の授業」実施校として、区立中学3校が産婦人科医を講師に授業を行う。性教育については、こうした実施校の取り組みや国の動向をふまえ、地域の実情や保護者の理解を得ながら段階的に進めていく。
2.外国ルーツの子どもの学習支援について
Q2-1. 80時間または120時間の取り出し授業を受けている子どもはどのくらいの人数か。今年度まで3年間の推移を伺う。国籍別ではどうなっているか、多い順に5つ伺う。
A2-1.教育委員会事務局次長)訪問指導・補充授業の日本語指導の対象となるのは、外国人と帰国した日本国籍の児童・生徒である。令和4年度108人、5年度133人、6年度152人で、国籍別では令和4年度はネパール、中国、フィリピン、アメリカ、インドネシア、5年度はネパール、中国、日本、フィリピン、アメリカ、6年度はネパール、中国、日本、フィリピン、ミャンマー、インドだ。
Q2-2.日本語の学習支援にあたっては子どもの状況を知るアセスメントが適切に行われることが重要である。教育委員会では子どもの力をどのように測っているか。
A2-2.教育委員会事務局次長)日本語指導担当の指導員が指導開始前と指導途中の2回、話す力・聞く力・読む力-書く力の4つの観点から総合的に定着度を確認している。具体的には子どもとの会話の内容や様子、子どもが書いた作文の内容、簡単な日本語に関する問題の出題、在籍学級での授業の様子、学級担任からの聞き取りを行っている。
Q2-3.「ことばの力のものさし」では「子どもの言葉の力の発達と日本語習得の二つの軸でとらえる。子どもの成長を見える化して支援に生かす」という点が特徴とされる。このような新たな方法について教育委員会の見解を伺う。
A2-3.教育委員会事務局次長)「ことばの発達と習得のものさし」については文部科学省が令和7年4月に出した評価の枠組みであると承知している。年齢に伴う認知的な発達を支えることばの力を包括的にとらえ、個に応じた指導・支援を行っていくことは重要であり、指導計画を立てるために有効であると考える。
Q2-4.日本語指導にDLAを取り入れていくことが推奨されている。DLAを取り入れたアセスメントについて教育委員会の見解を伺う。
A2-4. 教育委員会事務局次長)DLA(対話型アセスメント)は東京都教育委員会の日本語指導推進ガイドラインにもあるように、子どもたちの言語能力を把握し、個に応じた指導を検討するための評価ツールとして有効であると考える。
Q2-5.私は日本語教室でボランティアをするにあたって、最初に20時間、その後もブラッシュアップの研修を受けている。その研修が有意義で子どもと一緒に学ぶことの助けになっている。特によかったのが地球っ子クラブ2000の高柳なな枝さんを講師に招いた研修で、子どもがおかれている状況や気持ちを理解すること、自分の姿勢を省みること、彼らを日本の学校に適応させることに一生懸命になるのではなく、多様な経験、背景を持っている子どもの成長を考えることの大切さを学ぶことができた。このような研修は学校での日本語指導者にとっても有意義でぜひ聴いてもらいたいと思うがいかがか。
A2-5.教育委員会事務局次長)多様な背景を持つ子どもたちに寄り添いながら支援するためには、講師の資質・能力を高める研修は大切であると考える。教育委員会では年2回行っている研修会のさらなる充実に努める。
Q2-6.外国ルーツの児童・生徒の支援の進め方について、必要な児童・生徒には個別の支援計画を作って支援しているのか、またどのように作っているのか。
A2-6. 教育委員会事務局次長)各学校では個別の支援計画は作成していないが、支援が必要な児童・生徒には学級担任が中心となり、個に応じた指導を行っている。
Q2-7.外国ルーツの児童・生徒が日本語で学ぶために、授業や指導に「やさしい日本語」を取り入れることが有効だと考える。これは外国ルーツの子どもに限らず日本人の児童・生徒にも有効で、外国ルーツの子どもがクラスに在籍する教員が、やさしい日本語の研修を受けてもらいたいと思うが、その機会は設けられているのか。
A2-7. 教育委員会事務局次長)現在、教員に対してやさしい日本語の研修は行っていない。今後、東京都が作成している研修動画等を学校に周知していきたい。
Q2-8.外国ルーツの子どもがクラスに在籍する教員や、支援に関心がある教員が日頃の授業での工夫を共有したり、研修を受けたりする機会があるとよいが、教育委員会の見解を問う。
A2-8. 教育委員会事務局次長)学校では教員が日常的に行っている打ち合わせの中で、個に応じた指導について情報共有や意見交換を行っている。研修については国や都が開催する研修会の案内や資料を随時提供している。
Q2-9.令和6年第2回定例会で通訳ボランティアの派遣について質問したが、それは母語支援にあたる。通訳ボランティア制度の小中学校保育施設への周知と予算の確保を求めた質問に対して、周知に努めること、予算については関係課で協議していくと答弁があったがその後の進捗状況を伺う。
A2-9. 教育委員会事務局次長)通訳ボランティア制度については学校から相談があった際に紹介しており活用が少しずつ広がっている。予算については必要に応じて事業予算で対応している。
A2-9.子ども家庭部長)昨年の第2回定例会の質問を受け、その後に開催した私立保育園連絡会において、通訳ボランティア制度の周知を行い同年7月に利用実態調査を実施した。調査の結果、通訳ボランティア制度を知らなかったのが7割を占め、知っていたと回答した44施設のうち同制度を利用したのは1施設という結果だった。この制度を利用していない園の対応としてはスマートフォンの翻訳アプリを利用しているという回答が多く、そのほか日本語が話せる友人、家族がいるという回答だった。この結果、通訳ボランティアの予算は計上しなかったが、引き続き日本語でコミュニケーションをとることが難しい保護者への対応については通訳ボランティアや東京都が実施している多言語相談ナビの制度を周知して対応していく。
Q2-10.日常的に顔を合わせる外国籍の人たちに、母語支援の制度があることを伝えてもらいたい。区、教育委員会それぞれの考えを伺う。
A2-10.文化スポーツ担当部長)母語は個人が最初に自然に習得した言語で、家族から受け継ぎその人の思考や人格形成の基礎となるものだ。また、母語の基盤がなければ第2言語の習得が難しくなるともいわれる。区としては児童の健全育成や日本語学習の効果を高める観点から、母語でのコミュニケーションの重要性を外国人児童生徒及び保護者に対し、子ども日本語教室や外国語サポートデスクを通じて積極的に伝えていく。
A2-10. 教育委員会事務局次長)母語は普段の生活だけでなく、学習内容の理解力、思考力を伸ばすこと、自我の形成にも重要であると考える。教育委員会としては、外国ルーツの児童・生徒に対して日本語の習得だけでなく母語の重要性についても伝えていく。