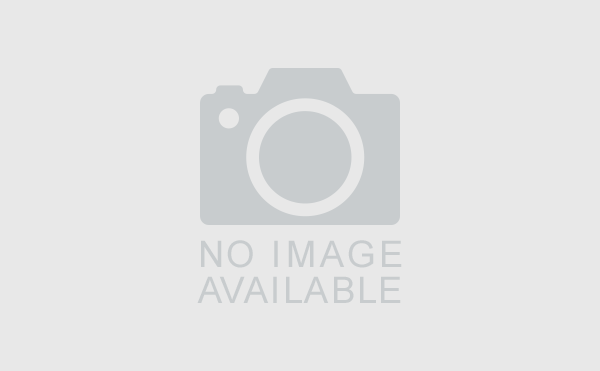第3回定例会一般質問と答弁 2025.9.11 奥田雅子
1.「きょうだい」支援について
Q1-1 今年の予算特別委員会で、病気や障がいのある人の兄弟姉妹を意味する「きょうだい」をテーマに質問したが、区が「きょうだい」なりの困難さをきちんと捉えていることが確認できた一方、「きょうだい」への支援が十分でないことも分かった。現場である地方自治体の中できょうだい支援の必要性を理解していかないと、どうしても後回しになってきたのではないかと感じている。子どもがおかれている状況は様々であり、ニーズも違うということを前提に誰も取りこぼさないためには、その実情を庁内全体で把握していくことが必要である。
区では、様々な子どもの実態をどのように把握し、制度やサービスにつなげているのか、伺う。また、つなげられる制度やサービスがない場合はどのようにするのか、伺う。
A1-1 (子ども家庭部長) 区では、これまで子どもに関わる各所管の職員が、日頃から子どもとの関係性の中で、様子を確認し声をかけ話を聞くことや、養育状況が心配との連絡が子ども家庭支援センターに入った場合の家庭訪問や面接、そのほか、子ども自身からの相談などを通じて、子どもの実態を把握してきたところだ。
そして、子どもの様子を見守る中で、サービス等の支援につなぐ必要があるときは、まずは子どもに支援の必要性を説明するとともに、保護者へ働きかけることについて理解を求め、保護者の同意を得ながら実施している。
また、つなげられる制度やサービスがない場合については、子どもの気持ちをしっかりと聴き、困ったときや聞いてもらいたいときは、いつでも相談してほしいことを伝えるなどの継続的な相談対応を行っている。
Q1-2 「きょうだい」の中にはヤングケアラーもいるかもしれないが、ケアを担っていなくても、きょうだいが抱える葛藤が様々あり、ヤングケアラーと地続きできょうだいの存在を意識していただけると良いのではないかと考える。ヤングケアラー支援に関する関係機関の研修にきょうだいという視点も盛り込み、きょうだいの心理や複雑な立場について理解できるような研修を求めるが、見解を伺う。
A1-2 (子ども家庭部長) 直接的に家族のケアをしていない「きょうだい」においても、ヤングケアラー同様に、家族への気遣いや、進路の選択を自ら制限するなどの心理的負担を感じている子どもが少なくないことは、区としても認識しているところだ。
区では、毎年、教育・障害・高齢・子ども分野等の関係課によるヤングケアラーのプロジェクトチーム主催で、関係機関向けの研修を実施している。
この研修の対象は、家庭内の状況を把握できる事業者等であることから、「きょうだい」についても理解を深め、ヤングケアラー同様に発見した場合は、必要に応じて相談機関につなげられるよう、研修内容を検討していく。
Q1-3 予特でも紹介した支援団体が作成しているリーフレットのようなツールの作成を検討するとのことだったが、特に子どもが相談してくるような窓口の案内にも「きょうだいの相談もできるよ」など、きょうだいが自分も対象なのだということが分かるような工夫をしてはどうかと考えるがいかがか。
A1-3(保健福祉部長) 「きょうだい」の中には、困難な状況であっても相談することをためらう方や、自身が「きょうだい児」であることに起因した困難さを自覚していない方がいることから、区としても自身がきょうだい児であることについて、その悩みについて相談できる窓口があることを知ることや気づきのきっかけを与えることは重要であると認識している。
このため、「きょうだい児」やその保護者が抱える様々な悩みをどこに相談すれば解決につながるかをリーフレット等に整理し、「きょうだい児」の可能性のある子どもやその保護者が相談等で利用する窓口において、必要となる相談、支援や「きょうだい児」の認知につながる取組を進める予定だ。
Q1-4 相談を受ける際に、その相談者に合った情報が提供できるよう、日頃から支援団体の発行する冊子や活動情報などを収集し、関係機関で共有する仕組みが必要と考えるが、見解を伺う。
A1-4(子ども家庭部長) 子どもと家庭の総合相談窓口「ゆうライン」や、子ども家庭支援センターにおいては、適切な相談対応ができるよう、日ごろから情報の収集や更新に務めている。「きょうだい」に関しても、障害者部門と連携をし、支援団体の発行する冊子や活動情報等の情報の収集等を行い、適切な相談対応ができるよう取り組んでいく。
Q1-5 支援団体の話では、きょうだい児支援、保護者支援、啓発の3本柱で活動を展開したいと思っても、全てを行っていくには限界もあるとのことだ。今後、区がきょうだい支援を行っていく際には、支援団体が持つ知識や経験を区と共有する中で、お互いの役割分担なども確認できると「きょうだい児」支援の継続性も担保できるのではないかと考えるが、区の見解を伺う。
A1-5(保護福祉部長) 区が「きょうだい児」支援の取組を充実していくためには、区内において、長年支援を行っている団体と意見交換などを行い、知識や情報の共有をすることは、非常に大切と考えている。このため、「きょうだい児」支援について、地域の支援団体と支援に係る役割分担等の確認を含む意見交換等の機会を今後とも設けるとともに。地域自立支援協議会などの地域の障害福祉について協議する立場からの意見など、地域の様々な声を聞きながら、必要な支援が地域で持続、充実できるよう、取組を進めていく。
Q1-6 学校現場においても「きょうだい児」という視点を先生方の意識に加えていただけたらと思うが、教育委員会の見解を伺う。
A1-6(教育委員会事務局次長) 子どもたちの生活の背景や家族の状況は様々で、そのことに起因して悩みや不安を抱えている場合もあり、「きょうだい児」としての悩みや不安も含まれると考える。学校では、こうした子どもたちの悩みや不安を、日常のかかわりやアンケート調査の中から見出し、組織的な対応を図っているところだ。
改めて、校長が教員の中から指名する教育相談コーディネーターの連絡会で、「きょうだい児」の視点について確認し、各学校への周知に取り組んでいく。
Q1-7 練馬区や板橋区、武蔵野市などは障害者計画や子どもプランにきょうだい支援が位置づけられ、交流会などの取組を始めている。今後、杉並区の障害者施策推進計画や子ども家庭計画にもぜひ「きょうだい」支援を加えていただきたく見解を伺う。
A1-7(区長) 障がい当事者への支援に加え、「きょうだい児」をはじめとする障がい当事者を支える家族や関係者の方々に対する支援を充実していくことは、区が、障がいの有無に関わらず、誰にとっても安心して暮らし続けることができる地域としてあり続けるため、重要な取組であると考えている。
こうした認識のもと、区では、「きょうだい児」について、障がい当事者と生活を共にする方を対象とするケアラー支援の課題の1つとして位置づけ、現在、その支援策等の検討を進めている。また、このような支援は継続的に検討し、取り組んでいくことが重要であると考える。その上で、令和9年度からの障害者施策推進計画等、今後の各計画における「きょうだい児」の位置づけ等については、以上の観点及び昨年度所管課で実施したケアラー支援に関する調査や今年度行う地域生活に関する調査等の結果も踏まえ、令和8年度に検討していく。
2.介護保険制度について
Q2-1 区内の訪問介護事業所数について、ここ3年間の推移を伺う。
A2-1(高齢者担当部長) 過去3年間における区内の訪問介護事業所数は、いずれも年度末時点で、令和4年度が146所、5年度と6年度は同数の153所となっている。
Q2-2 介護事業所の実態把握については、現在高齢者等実態調査の中で実施していると思う。今回の調査は内容を見直し、より実態がわかるような設問にしていると認識しているが、具体的にどのように見直したのか確認する。
A2-2(高齢者担当部長) 前回調査の内容に加え、介護職員の充足状況や、今後の人材確保・人材育成の方策と区に望む支援策、現在の経営状況と必要な経営支援策に関する設問を設定するなど、より実効性が高い内容となるよう抜本的に見直した。
Q2-3 小規模事業所ほど事業経営が厳しいこと、人員不足と職員の高齢化、ヘルパーの地位向上と基本報酬アップなど、生活者ネットワークが実施した調査で見えてきた課題に対して、区はどのように認識したか見解を伺う。
A2-3(高齢者担当部長) 昨年の夏から秋にかけて東京・生活者ネットワークが実施した「訪問介護事業所の運営に関する実態調査の分析報告」では、小規模事業所と大規模事業所の二極化が進んでいることや、多くの事業所が人材不足を感じていることなど、厳しい経営環境にあることが示されており、今後、区の実態調査結果を集計・分析する際の参考にさせてもらう。
Q2-4 今議会で上程されている補正予算において、物価高騰対策として615所の介護サービス事業所に6406万2千円が計上されたが、食材費や光熱費等の一部に対する助成であり、訪問・相談系の事業所には効果的な対策とはならないのではないかと感じた。区独自の事業所への直接給付についてどのように検討した結果、今回のような提案に至ったのか伺う。
A2-4(高齢者担当部長) 今定例会で提案している補正予算に計上した、区内介護サービス事業所に対する食材費・光熱費等助成については、既に東京都が実施している物価高騰緊急対策事業の助成対象となっていない事業所を対象に同等の内容による助成を行い。物価高騰に直面する事業所を区独自に支援することとしたものだ。
Q2-5 区は訪問介護員の人材確保のためにはどうすればよいと考えているのか見解を伺う。
A2-5(高齢者担当部長) 第一義的には、国が多様な事業者の声や保険者である区市町村の意見を聴きながら、介護報酬の改定を適切に実施することが重要と認識している。そのため、区としては、引き続き、全国市長会等を通して国に強く働きかける一方、国や東京都の動向等を考慮しつつ、訪問介護など区内介護事業所の人材確保等に資する区独自の支援策を、適時適切に検討・実施していく必要があると考えている。
Q2-6 1年前、区は総合事業について「現在、関係部門が連携して、事業の検証と課題の洗い出し、今後の方向性やそのための組織体制の在り方などの検証に着手した」と答弁している。財政制度等審議会で要介護1・2を地域支援事業に移行することをめざすとしているが、それについても区の議論の中で話し合われていると推察するが、今後の総合事業についてどのような見解になっているのか伺う。
A2-6(高齢者担当部長) この間、高齢者部門と保健サービス部門が連携して、これまでの総合事業の検証・評価と令和8年度以降の見直しの方向性を検討してきており、取りまとめまで、あと一息という状況に至っている。
現時点における、見直しにあたっての基本的な考え方は、主に要支援1・2の人を対象とする総合事業を拡充して、より一層、対象者の健康維持・増進や介護度の中重度化の抑制を図ること、住民全体の活動及び集いの場を増やして総合事業の機会と場を拡充し、区が目指す地域共生社会の実現につなげていくこと、の大きく2点に整理しており、議員からの指摘にあった「要介護1・2の人を介護サービスから総合事業へ移行させること」を念頭に置いたものではない。
今後、検討結果を庁内取りまとめの上、必要事項について、令和8年度当初予算編成等への反映を図っていきたい。
Q2-7 利用者負担割合が原則2割となることで、利用控えにつながり、重度化がすすみ家族等の介護者の負担が増大し、介護離職の増加も懸念される。また、ケアプラン有料化はケアマネジメントの利用抑制につながる懸念があり、要介護者の状態変化の早期発見・早期対応が困難になり社会的負担が増大するおそれがある。利用者負担割合原則2割およびケアプラン有料化について区の見解を伺う。
A2-7(高齢者担当部長) 「利用者負担原則2割」と「ケアプラン有料化」については、議員が指摘したような懸念があるため、直ちに国民的な合意を得ることは難しいのではないかと考えている。
Q2-8 国は持続可能な制度のことばかりで、高齢者の持続可能な生活という視点が欠落している。介護保険制度の問題は自治体共通の課題なので特別区長会や介護保険課長会などから東京都や国に働きかけていく動きはないのか。当事者、ケアラー、事業者、地域の支援者の生の声を聞き取り、地域の実情を把握した上で他自治体と連携し東京都や国に意見を上げてほしいと思うが区の見解を伺う。
A2-8(高齢者担当部長) 議員の「高齢者の持続可能な生活という視点が大切」という指摘は区としても同感であり、今後とも特別区高齢者福祉・介護保険課長会等で各区の実情や問題意識の共有を図りながら、適宜、国や東京都へ意見・要望していきたい。